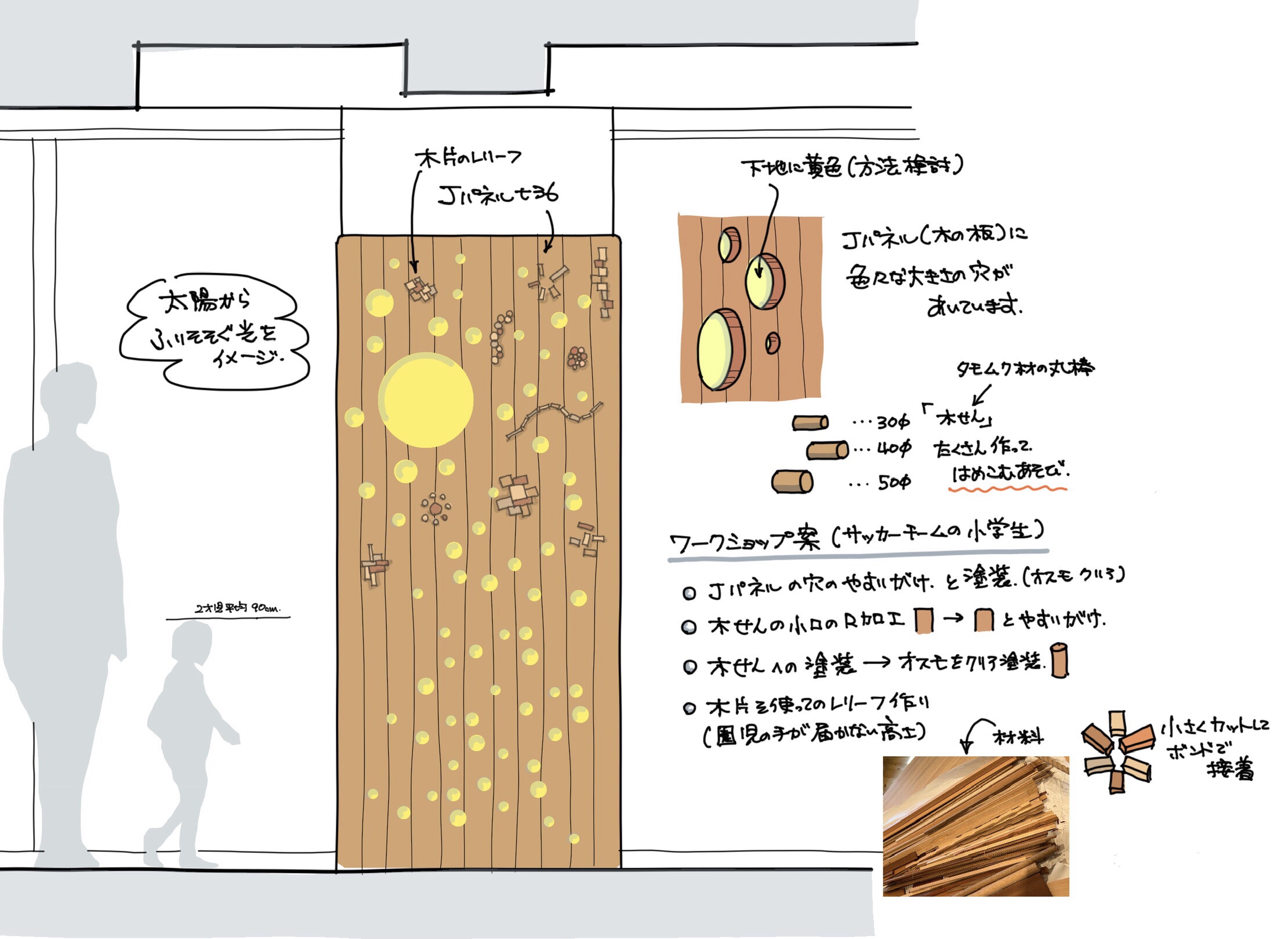2月下旬に東村山の保育園、3月上旬には昭島の福祉施設の見学会が開催された。天候が悪い中多くの方々にお越しいただき、事業者関係の方々のご協力や、相羽建設のスタッフの皆さんのご尽力にも最大限の感謝を申し上げたい。
両見学会とも、15分程度の計画のプレゼンの機会をいただいた。発表する内容をスライドにまとめたり、「見どころMAP」という計画コンセプトをまとめた配布資料を作成するなどの作業は、あらためて計画への想いを整理する大切な作業のように思う。

計画のスタートから施主に対し計画のコンセプトを説明しながら設計が進むが、計画開始から竣工まで2年近く経過するとその過程のなかで考えが少し変わったり、詳細な設計作業により細かい要素が加わるなど、当初のコンセプトがあいまいになる場合がある。そんな中、工事が終わったタイミングでの発表機会は計画を見つめ直す時間になるのだ。
初めて事業者と顔を合わせた日、第一案を提出した打合せ、数案を示した過程、実施設計過程、地鎮祭や上棟などのお祭りや工事過程など、一通り振り返りながらいろいろなこと思い出し、作業がなかなか進まなかったりもする。
ようやく完成したプレゼンだったが、自身の口下手でお聞き苦しかったことをお詫びしたい。