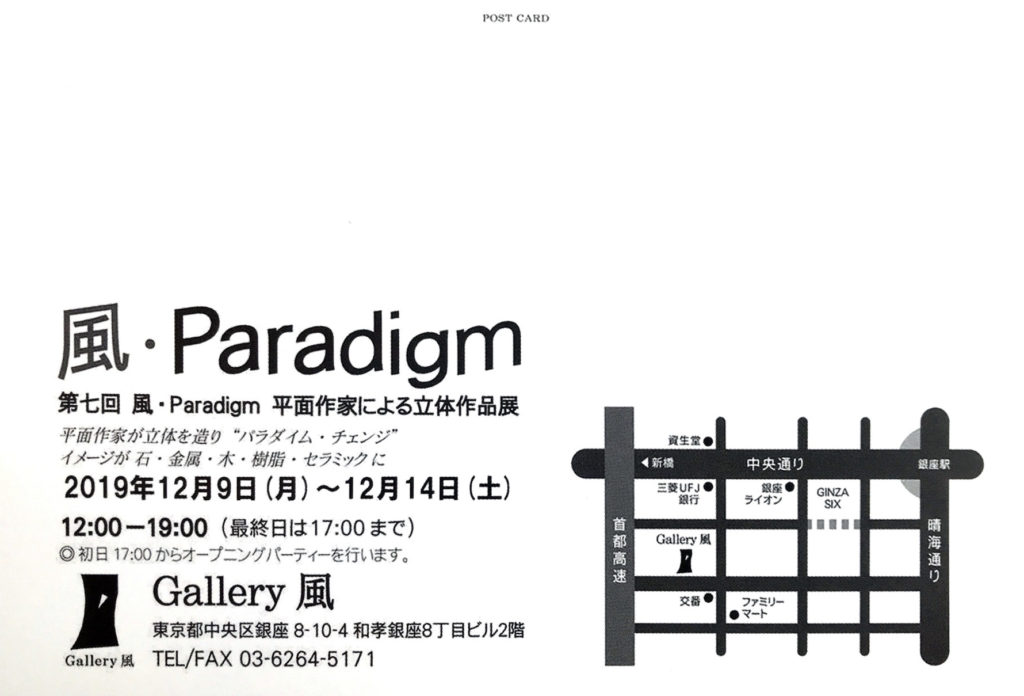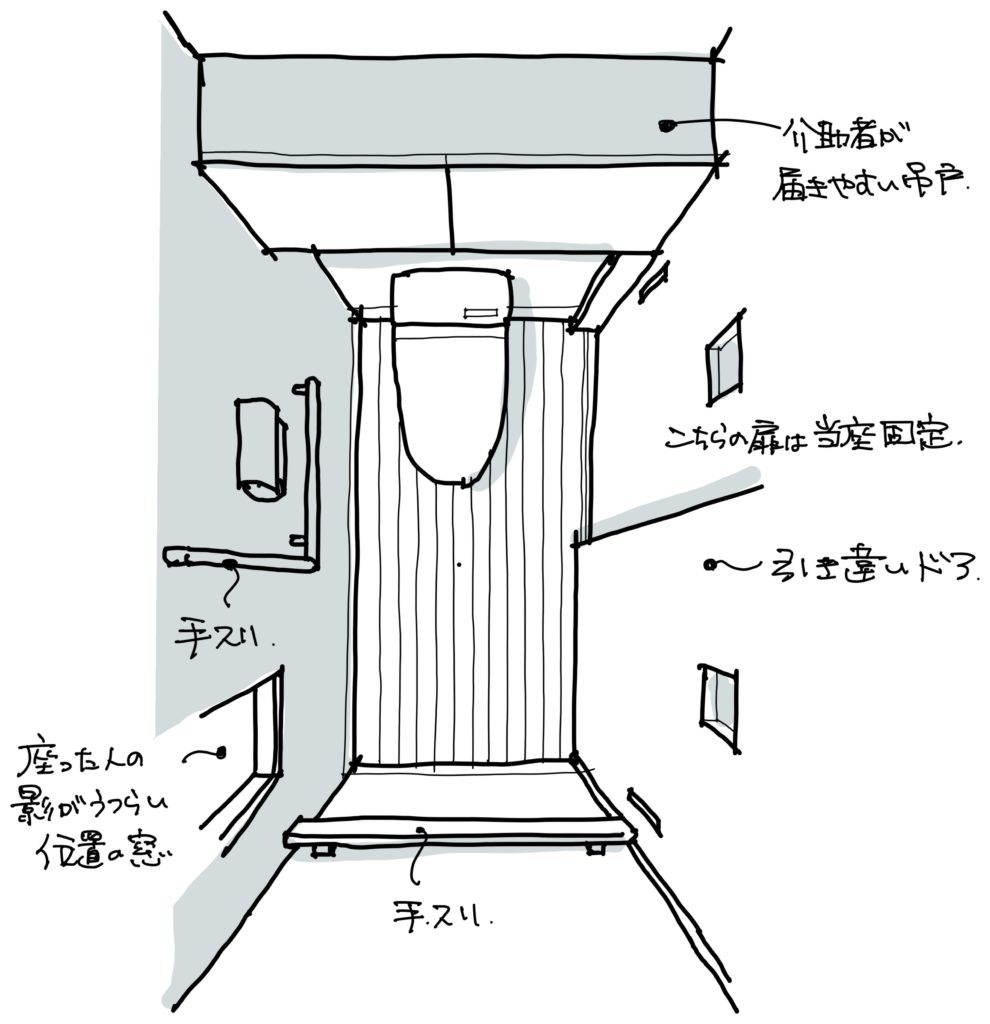以前、海外で感じた街であふれる会話の想いを書いた。その続き。
先日、フランス・ボルドーを訪れた。ワインの街ボルドーにはワイン専門の博物館がある。まずは建築、XTUアーキテクツの設計。郊外の再開発エリアにあるその建物は、エスカルゴの様な、デキャンタの瓶の様な複雑な曲線で構成された建物。写真での印象とは違って圧迫感を感じるような巨大建築ではなく上手くスケール感を調整していると思う。外部の印象より内部が広いと感じた。

建築も斬新だが、展示物も経験したことがない展示手法だった。入口でスマホ大の端末とヘッドフォンを渡される。一般的に美術館などの有料音声ガイドは補助的な解説用であり借りなくて展示は楽しめるが、この博物館ではその端末がないと成立しない。至るところに端末をかざす印があり、近づけると音声が流れてくる。ほとんど文字情報のパネルなどは見当たらず、各展示物は端末からの音声で情報を受ける。一見何の展示が分からなくてもその印を探して解説を聞きながら楽しむ、その行為が展示に対しなんとなく能動的に参加しているような気持ちなるのだ。

その端末は 日本語など20か国に対応しているが、ついでに作った感は全くなく、翻訳家や脚本家、複数の声優などきちんとした日本語録音チームによって制作されたのは想像に難くなくとてもクオリティーが高い。展示量はとても多く、それを20カ国分あるのだからコストと手間は膨大だっただろう。そのあたりが言葉を重んじる国民性の良さかなと思うだが、さらに印象的な展示があった。

細長いダイニングテーブルがあって、ワイングラスやお皿を模したオブジェが乗っている。その周りに背もたれが高い椅子が並んでいてそのうちの2つの背もたれがディスプレイになっている。その画面には若いソムリエともう一方には客の紳士が映っていて、ワインについて熱く語り合っているのだ。空いている椅子に座っているとあたかもどこかのレストランでふたりの会話に参加しながら食事しているような錯覚になる。わざわざその雰囲気作りをする発想がとても興味深い。やはりワインは重要なコミュニケーションツールということなのだろう。

他にこの博物館ではワインの試飲もできる。試飲と言ってもワイングラスで通常に量なので弱いわたしはしっかり酔ってしまった。